| お江戸のおもしろグッズ【5】 『江戸切子のさりげない豪奢』 | |
| 文・絵 三輪映子 | |
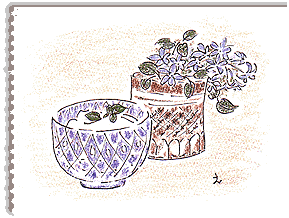 「キリコ」、なんて素敵な響き。それはカットされたガラス器の、幾何学的に交錯する光の印象そのものに感じられる。どこのどなたか知らないけれど、この言葉を考えた人のセンスに敬意を捧げ、小さな切子の一つ二つを日常の器に加えよう。視覚の美と言葉の美とが奏でる、イメージの二重奏を楽しみたい。 「キリコ」、なんて素敵な響き。それはカットされたガラス器の、幾何学的に交錯する光の印象そのものに感じられる。どこのどなたか知らないけれど、この言葉を考えた人のセンスに敬意を捧げ、小さな切子の一つ二つを日常の器に加えよう。視覚の美と言葉の美とが奏でる、イメージの二重奏を楽しみたい。ガラスをカットする技術は古代からあった。ササン朝ペルシャのカット・ガラスは、はるばるとシルクロードを運ばれ、正倉院に「白瑠璃碗」としておさまっている。それくらいだから、カット・ガラスは、各時代、世界各地で作られてきた。そのなかで、江戸切子の個性とは? 「華硝」の熊倉隆一さんにお話をうかがった。 江戸時代の人々はガラスが大好き。オランダ渡りのビードロ杯や板ガラスから、町なかの職人が作る風鈴や金魚鉢と、懐具合に応じて、それぞれに楽しめるガラス製品があったらしい。江戸切子はそんな土壌から生まれた。やがて明治になり、江戸切子も文明開化の洗礼を受ける。素材のガラスが変わり、工具が変わった。しかし変わらないものは、職人の心意気。重厚さよりは瀟洒をよしとし、実用品としての使いやすさを大切にする。熊倉さんは江戸切子の技術者にしてデザイナー。亀戸天神のお膝元に工房を構え、日本の伝統的な柄ゆきを生かしながら、現代生活になじむ江戸切子を追求している。 絵は、私が一目惚れした薄紫の小鉢。プレーンヨーグルトにミントの葉を添えて。 |
前ページ / 次ページ
| 江戸最新情報 | 江戸の商い | 江戸おもしろグッズ | かわら版 | TVZ表紙 |